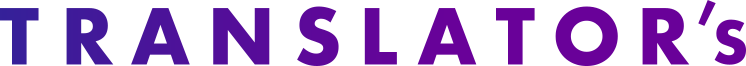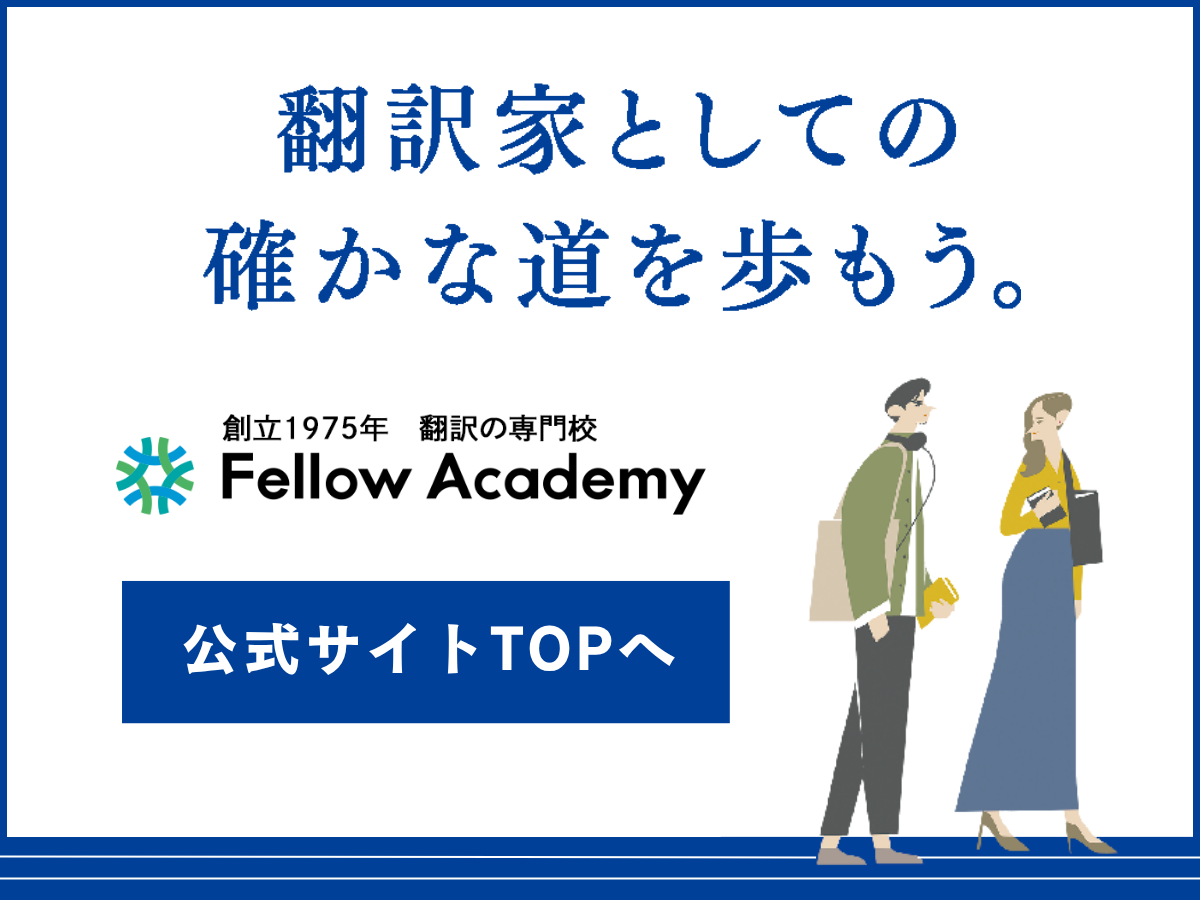OTHERS
ポストエディットとは?やり方や種類、メリット、注意点を解説!
本記事ではポストエディットについて解説します。ポストエディットのやり方や種類、メリット、注意点についてまとめました。
翻訳に関わりたいと思っている方はぜひお読みください。
ポストエディットとは?

ポストエディット(Post-Editing)とは、一般的には機械翻訳によって出力された訳文を翻訳者がクライアント(翻訳発注者)の希望に沿っているか確認、修正する作業を指します。
昨今はAIの進化が著しく、それに伴って機械翻訳の精度も向上しています。少し前まで機械翻訳によって訳された文章は読みにくく、精度にも問題があり、使い物にならないことがほとんどでした。しかし今では実用レベルになっているため多くの翻訳会社が導入し、「機械翻訳+人の手によるポストエディット」という形での受注が増えています。
そのためポストエディットのスキルを身につけることは、翻訳者にとって必須事項になっていくと言えます。
人力翻訳とポストエディットの違い
人力翻訳とは翻訳者が一から翻訳作業を行うことを指します。原文および参考資料を元に、文章の目的や書き手の意図を理解し、読み手に配慮しながら訳します。翻訳会社に納品した後は、チェッカーやQA(Quality Assurance)の担当者が、訳抜け、用語統一、表記ルールなどさまざまな観点からクライアントの意向に沿った翻訳文になっているかを確認します。
一方で、ポストエディットは、最初に原文を機械翻訳に取り込んで翻訳します。翻訳者は機械によって訳された文章に、クライアントの品質要求に応じた修正を加えます。品質によって「ライトポストエディット」「フルポストエディット」と呼び分けされることもあり、この二者の違いは後述します。
ポストエディットが必要な理由

ポストエディットが必要な理由は翻訳の品質を担保するためで、大きく2つの役割があります。
- 正確性を高める
- クライアントの意向を反映させる
それぞれ解説します。
正確性を高める
機械翻訳を使用した翻訳文は必ずしも正確ではありません。AIは誤訳のパターンが予測不能であり、原文の一部を丸ごと抜かして訳すこともあります。また「ハルシネーション」といって、原文に無い情報を生成してしまうこともあります。これはAIが学習データからの推測を誤ることで発生します。
また文脈や意図を踏まえることができないために、適切な翻訳を出力できない場合もあります。
こうした機械翻訳のマイナス面は翻訳の品質を大きく損ねてしまうため、人の手によるポストエディットが欠かせません。
クライアントの意向を反映させる
機械翻訳を使用するメリットはコストダウンやスピードです。
ポストエディットによって人間翻訳と同等の品質を目指すことも可能ですが、それであれば最初から人間が訳しても変わらないため、効率が良い方法とは言えません。
つまり、機械翻訳+ポストエディットでは、最終的に求める翻訳品質において、どのレベルまで許容し、どの水準を満たしたいかという、クライアントの意向がとても大切です。
例えばある文書の翻訳では必ず指定用語を使う必要があり、日付や時間といった数字のミスはあってはならないけれど、コストを抑えるため読みやすさは二の次で良い、というケースもあり得ます。
翻訳上のルールはクライアントから「スタイルガイド」「用語集」といった資料で提供され、指示どおりに翻訳されているか、クライアントが優先したい部分が守られた翻訳になっているかをポストエディットで確認する必要があります。
ポストエディットの種類と具体的なやり方

ポストエディットには大きく次の2種類があります。
- フルポストエディット
- ライトポストエディット
翻訳者はクライアントが求める翻訳の質や翻訳スピードによって、これら2つを使い分ける必要があります。
それぞれのポストエディットの種類と具体的なやり方を見ていきましょう。
フルポストエディット
「フルポストエディット」は、プロの翻訳者による翻訳と同等レベルの品質を目指すポストエディットです。といっても特にどの要素を優先すべきなのか――読みやすい文体なのか訴求力のある言葉選びなのか、とにかく正確さが最優先なのか――は、文書の種類や目的、クライアントの意向によって異なります。翻訳者はやみくもに修正を加えるのではなく方針を確認した上でポストエディットを行う必要があります。
ライトポストエディット
「ライトポストエディット」は、フルポストエディットに比べると翻訳のスピードやコストを重視する場合に採用される手法です。翻訳の品質基準のうち、優先度の低い要素を省略したり簡略化したりします。誤訳さえ無ければ良しとして、表記のゆれや用語統一は求めないケースもあります。
ポストエディットのメリット
機械翻訳とポストエディットの組み合わせで翻訳を行うメリットは大きく2つです。
- 翻訳コストを下げられる
- 翻訳スピードを早くできる
この2つのメリットはクライアントにとって魅力的なため、対応できる翻訳会社は売上の向上が見込めます。ひとつひとつのメリットについて解説します。
翻訳コストを下げられる
機械翻訳を活用しない場合、翻訳者が納品した翻訳原稿を、翻訳会社あるいは社外のチェッカーがチェックします。翻訳者だけでなくチェッカーの人件費までかかってしまいます。
ポストエディットは、機械翻訳を行った後の修正で、主に翻訳者が行います。翻訳者がチェッカーの役割も果たすため、基本的にはチェッカーを必要としません。
またポストエディットは一から翻訳するより作業範囲が限定的なため、その分翻訳者に支払う報酬も抑えられるケースが多いです。
翻訳スピードを早くできる
人の手であれば何日もかかってしまう翻訳も、機械翻訳にかければ数分足らずで翻訳できます。
その後翻訳者がポストエディットを行ったとしても、トータルで費やす翻訳日数はかなり短縮することができます。
ポストエディットについて学ぶ方法

最後に、ポストエディットについて学ぶ方法について解説します。
機械翻訳が実用レベルになり広く活用されるようになったのはここ最近のことです。そのためポストエディットのスキル習得に関する情報はあまり出回っておらず、方法が分からない方も多いかと思います。
ポストエディットについて学ぶおすすめの方法は次の2つです。
- 翻訳学校に通う
- 通信講座を活用する
翻訳学校に通う
1つ目は翻訳学校に通うことです。翻訳学校とは翻訳者を目指す方が通う学校のことです。最近ではオンラインで参加できる講座も多くあり、校舎が近くにない方も受講できます。
翻訳学校によってはポストエディット講座を設けています。
もちろん、ポストエディット以外の翻訳スキルも習得できます。ポストエディットと翻訳のスキルは重なる部分が大きいため、翻訳スキルを磨けばポストエディットに応用できるしょう。
通信講座を活用する
2つ目は通信講座を活用することです。現職が忙しいなどの理由で、翻訳学校の講座に参加できないという方もいるかと思います。そのような方には通信講座がおすすめです。
通信講座なら自分のペースで勉強を進めることが可能です。たとえば、会社の休み時間や通勤時などの隙間時間に勉強することもできます。
ただし通信講座は基本的には一人で教材を進めるため、モチベーションの管理が重要です。モチベーションを管理できれば、通信講座でもプロの翻訳者を目指すことができます。
まとめ
本記事ではポストエディットについて解説しました。ポストエディットが必要な理由やメリット、注意点などがお分かりいただけたかと思います。
機械翻訳の質は年々向上しており、今や実務で通用するレベルになっています。機械翻訳を活用すれば、翻訳コストを下げられるうえに、翻訳スピードも早くすることが可能です。ただ、機械翻訳はまだ完璧ではないため、翻訳者がプロの目で確認・修正を行います。
ポストエディットのスキルは今後更に重要性が高まることが予想されます。翻訳者を目指す方は今のうちにポストエディットのスキルを身につけることをおすすめします。
翻訳家を目指すならフェロー・アカデミーへ!
仕事に繋がる翻訳スキルを学ぶなら、翻訳学校がおすすめです。
翻訳学校であれば専門知識と翻訳の実務経験を持つ講師から指導を受けることができ、学習中の疑問点もすぐに解決できます。
また最適化されたカリキュラムのため無駄がなく、効率的に学ぶことが可能です。
「フェロー・アカデミー」ではライフスタイルやレベルに合わせて講座を選ぶことができ、必要な知識やスキルの習得、仕事獲得までサポートが受けられます。
学校パンフレット(電子ブック)をPDFで閲覧できますので、最速で翻訳家を目指す方はぜひお気軽に資料請求ください。コース別の説明会、プラン選びのための学習カウンセリングも実施しています。
この記事の監修

その後、翻訳者を志し退職、フェローアカデミーの「ベーシック3コース」を修了し、翻訳者として5年間活動した後、翻訳者ネットワーク「アメリア」立ち上げに参画、理事長/代表取締役に就任。