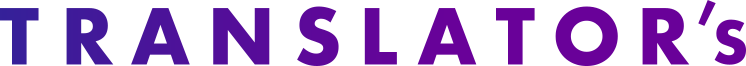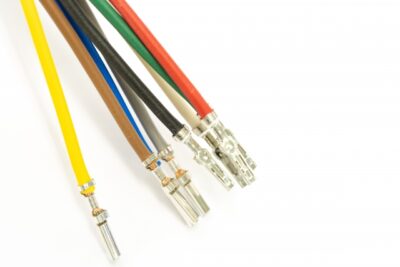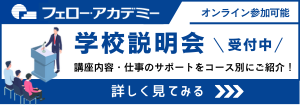WORKS
メディカル文書の中でも新人需要の高い「治験翻訳」とは?
海外で開発された薬であれば日本向けに、日本で開発された薬であれば海外向けに、治験概要やその結果を国のガイドラインに則って翻訳する必要が出てきます。
治験のプロセスにともなって発生する翻訳文書は実にさまざま。まずはメディカル翻訳者を目指す方にぜひ知っておいていただきたい、代表的な文書をご紹介します。
INDEX
メディカル翻訳の対象となる代表的な文書
- 治験薬概要書
治験の実施を依頼する製薬会社などが、治験を実施する医師に向けて作成する文書。治験薬の特性や、過去に実施された試験の成績などがまとめられている。
- 同意説明文書
被験者候補となる患者に向けて作成される文書。患者はこの文書を読んで治験の内容を理解し、治験に参加するか否かを決める。
- 治験実施計画書(プロトコル)
治験の目的、実施方法、被験者の選択・除外基準、統計解析手法など、治験の実施に必要な情報が書かれた計画書。日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)で定められたガイドラインにもとづいた書式で項目立てが行われるのが普通。
- 症例報告書
治験責任医師などが、被験者の情報を治験依頼者に報告するために記録する用紙。
被験者のイニシャル、年齢、性別のほか、治験薬の投与状況や有害事象(医薬品を摂取した人に起こる“あらゆる好ましくない出来事”)の発現状況などに関する情報が記録される。
- 治験総括報告書
治験の結果を報告する文書で、治験実施計画書の内容に治験結果が追加されたものといったイメージ。
治験に関する文書は、用語の定義や書式がICHガイドラインに準ずる場合が多いため、翻訳の際にもそれを参照することが必須です。また正確な訳をすることに加え、被験者候補となる一般の方に向けた「同意説明文書」は平易な表現で読みやすく訳すなど、ときには読み手を意識した工夫も求められます。
新薬の開発・承認申請が世界規模で行われる昨今では、複数の国で同時に治験を行う国際共同治験(グローバルスタディ)という方法もとられ、和訳・英訳をスピーディーに行う場面も増えています。
いずれにせよ新人需要が多いため、ぜひ押さえておきたいのが治験翻訳。実際に案件を受注している翻訳会社の方に、このジャンルを目指す方へのメッセージを伺いました。
代表的な治験実施計画書以外にも関連文書はさまざま。新人の方はそれらの案件にも対応できると仕事獲得につながります
――株式会社メディカル・トランスレーション・サービス 穴見翼さん
医療翻訳といえば治験実施計画書が代表的な文書ですが、治験が行われる過程ではそれ以外にも多くの文書が用いられます。
実際に治験が始まる前の文書としては、計画段階での規制当局とのやり取りである「機構相談・照会事項」、治験依頼者が実施医療機関と締結する「治験契約書」、治験責任医師や実施医療機関向けに治験薬の情報を記載した「治験薬概要書」のほか、開始前のトレーニング資料など。
治験が始まってからの文書としては、参加する方に治験について説明する「同意説明文書」、参加者ごとに治験関連のデータを収集するための「電子症例報告書(eCRF)」、治験依頼者から実施医療機関への事務的な連絡である「レター」、発生した副作用を当局に報告する「個別症例安全性報告」や臨床検査のものをはじめとする各種のマニュアルなどなど。
弊社は「メディカル・トランスレーション・サービス」という社名が表すように、医療分野を専門として翻訳サービスを提供しています。
クライアントから治験実施計画書の翻訳を依頼される場合、その前後に、同じ治験に関連する上記のような文書の翻訳も付随して依頼されることがとても多く、そうした文書を合わせると、受注する案件に占める割合は治験実施計画書よりも多くなります。
また、治験実施計画書はボリュームもあり、重要性も高いためベテランの翻訳者さんに依頼しがちで、新人の翻訳者さんにお願いする機会はどうしても少なくなってしまいますが、分量の少ないその他の文書であれば新しい方にもお願いしやすいです。したがって、「①案件自体が多い、②新しい方にも依頼しやすい」という2点から、治験実施計画書以外の治験文書に対応できることは、医療翻訳でお仕事を得る機会につながるといえます。
また、治験に関する基本的な知識があることが前提にはなるものの、契約書の翻訳経験がある方であれば「治験契約書」、ビジネス文書一般の翻訳経験がある方であれば「レター」やトレーニング資料など、治験実施計画書以外の文書は医療翻訳以外の分野の翻訳経験が活きやすいお仕事でもあります。
そうした文書で良い翻訳を出してくだされば、「今度は治験実施計画書を……」とお仕事が広がっていく可能性もあります。一方で、なじみのない文書を「大丈夫です、できます」と引き受けていただいても、十分な品質の翻訳をご提供いただけない場合、次の依頼が遠のくこともあります。
上記の文書は、治験実施計画書を基本とはするものの、特徴や翻訳する上で注意すべき点がそれぞれに異なり、予備知識なしできちんとした翻訳をするのは簡単ではありません。弊社がフェローで担当している「翻訳会社ゼミ」では、「治験薬概要書」、「個別症例安全性報告」、「eCRFのマニュアル」を取り上げ、その基本的な情報と翻訳上の注意点を説明しています。また、事前の課題や授業中の例題が、実際にその文書に出てくる文章に触れ翻訳する機会となります。特に事前の課題では、一人ひとりの受講生の訳文を丁寧にチェックし、翻訳に役立つアドバイスとなることを願ってコメントを付記しています。
➡メディカル・トランスレーション・サービスが担当する講座「翻訳会社ゼミ(臨床試験)」の詳細を見る
取材協力
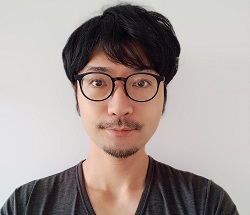
- 穴見翼さん
- 東京大学言語文化学科卒。(株)メディカル・トランスレーション・サービス勤務。2008年の入社以来、一貫して医療翻訳に携わる。現在は、品質保証部門の責任者として、翻訳・チェック業務のほか、社内外の人材の教育研修などに従事している。

- 株式会社メディカル・トランスレーション・サービス
- 1999年の設立以降、メディカル分野に特化した翻訳を一貫して行う。東京、大阪に拠点を置きメディカル翻訳におけるオンリーワンを目標に、医療の発展の一助となり広く社会に貢献できる企業を目指す。
株式会社メディカル・トランスレーション・サービスのWebサイトはこちら
原文と訳文の一言一句対応に加え、きちんとした文にすることも重要。その点では文系出身者にも有利といえます
――トランスパーフェクト・ジャパン合同会社 福岡由仁郎さん
治験にかかわる基本的な文書となるのが「治験実施計画書」です。
弊社では新人のリンギスト(翻訳者)の方に、治験実施計画書をベースに何かを提案、変更したり、あるいはそれに従って報告したりするような、ややボリュームの小さな文書から翻訳を依頼することが多いです。
また現在はCAT(翻訳支援)ツールを使用する案件がほとんどですし、新人の方にはMS Wordの変更履歴を使って過去訳を修正する案件を依頼することもあります。
翻訳で大事なのは、原文と訳文を一言一句対応させることです。
治験文書はグローバル版から各国語版に展開されていきますが、そのなかで、ある言語版で書かれている情報にばらつきが出ると、全体の整合性がなくなるのです。もし直訳でぎこちなくなってしまう場合は、係り受けを意識しながら、句構造をまとめてブロックにしたり、語順を適切に処理することで読みやすくなるように対応します。
また参考資料(過去バージョンの文書など)と細かい部分まで付き合わせて整合性を確認できる人は重宝され、特定のクライアントから専任で依頼を受けられるようになると思います。
実際に案件をとるようになっても、数年間は学ぶことのほうが多いぐらいかもしれません。弊社ではリンギストが必要な情報を迅速に取得できるように、各種ガイダンスを取りまとめてライブラリ化しています。動画モジュール形式のシステムも完備していますし、ときには参加者を募って、テーマ性を持ったクラスルームトレーニングを実施しています。
翻訳者を選定するトライアルの段階では、評価者の主観的な判断のバラツキを避けるため、減点方式をとっている企業が多いと思います。そうなると細かいミスの数が評価に影響しやすいですよね。トライアルの際には、コロケーションやコンテキストに応じた訳し方に注意するようにしてください。訳漏れや専門用語ミスは誰しも気づける部分ですが、もうすこし微妙な語感を意識して翻訳できるかどうかが判定結果を分けるかもしれません。
この分野の翻訳は理系出身者が有利と思われがちですが、必ずしもそうとは言えません。どんなに理系の背景があっても、主語、述語、係り受け、抑揚等、きちんとした文になっていなければ、品質が低いと判断されるのです。つまり医学・薬学の専門用語をきちんと押さえていることに加え、サッと読めるこなれ感、そして規制要件に関する一定の知識が揃っていることが重要です。
文系の方は1点目の専門知識のラーニングは必要ですが、時間をかけて取り組んでいけば達成できると思いますし、2・3点目に関しては有利といえるでしょう。いっぽう文系側で特に学びにくく、それでいて極めて重要なものが「医療統計」です。
弊社が担当する講座では、新人に依頼されやすい治験関連文書の種類や用途、正確かつ読みやすい翻訳表現の工夫、CATツール、さらには医療統計など、さまざまなトピックを盛り込むようにしています。今は昔と比べて自分でリサーチして得られる知識も格段に増えていますが、課題の解説では一人だと気づきにくい観点をとりあげ、皆さんの学習のよいサプリになる内容を心がけています。
千里の道も一歩から。ぜひ志してみてください。
➡トランスパーフェクト・ジャパンが担当する講座「翻訳会社ゼミ(臨床試験)」の詳細を見る
取材協力

- 福岡由仁郎さん
- 東京外国語大学大学院博士後期課程修了(Ph.D)。国内LSPに入社し、ライフサイエンスチームを立ち上げる。2012年よりトランスパーフェクト・ジャパンにてプロジェクトマネジメントチームを統括。2017年以降は品質管理、プロセス開発、ベンダー管理などのチームでリードを務める。

- トランスパーフェクト・ジャパン合同会社
- トランスパーフェクトは、北米、ヨーロッパ、アジア各国に、10,000名を超える言語スペシャリストとプロジェクト管理スタッフを擁する世界最大のランゲージ・ソリューションサービス・プロバイダー。東京では国際的な協力体制のもと、日本市場・日本語に特化したチームを編成している。
主要顧客は国内・国外のグローバル企業であり、言語コンテンツマネジメントシステムや人工知能を含む言語テクノロジー全般の開発に特に力を入れている。
トランスパーフェクト・ジャパン合同会社のWebサイトはこちら