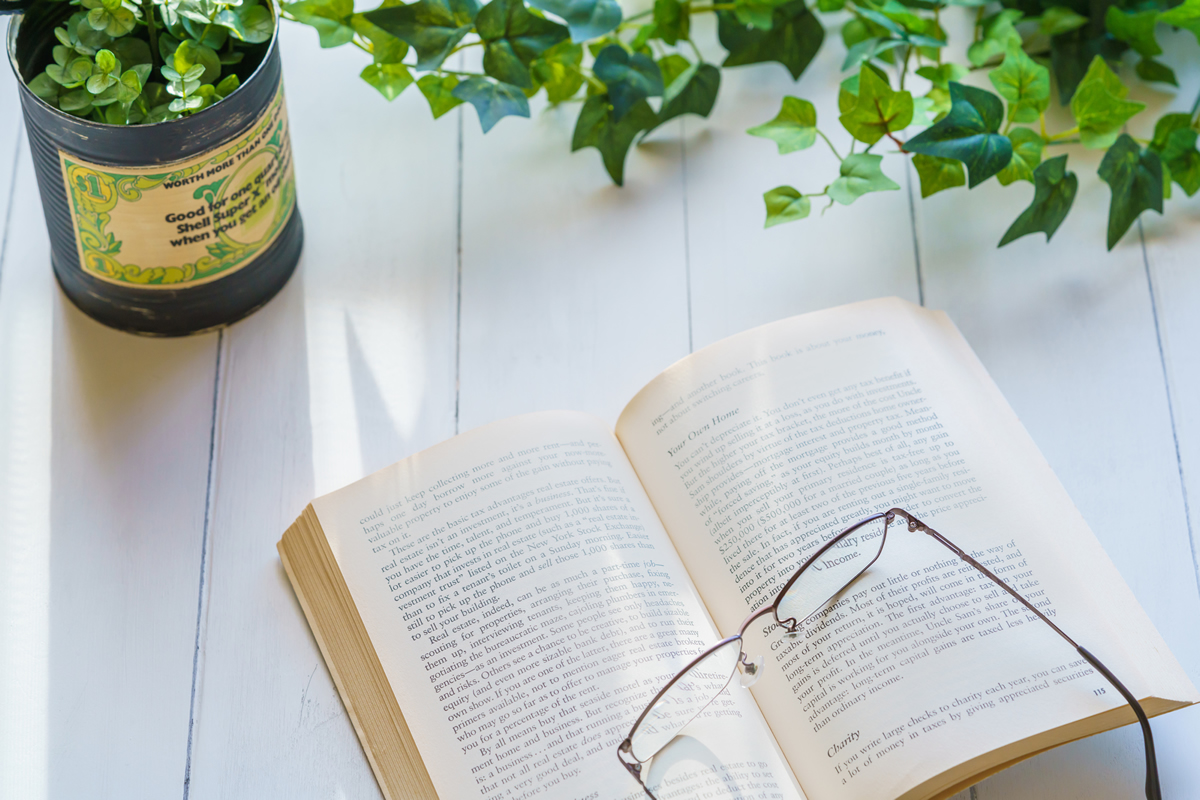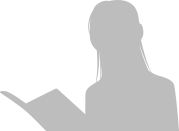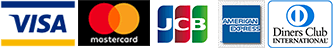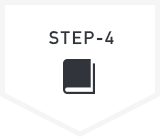コース概要
- 受付開始日
- 8/1正午
- 講座名
- 出版翻訳コース初級 出版基礎(1)
- 受講形式
- ライブ配信(アーカイブ配信あり)
- 受講期間
- 2025/10/24~2026/2/13(毎週×15回)
- 受講料
- 149,600円(税込)
- 曜日・時間
- 金曜・19:00~21:00(120分)
- 定員
- 10名
- 修了規定
- 全授業回数の7割以上出席
- 申込締切
- 9/29
- 教材について
- 教材はデータでのご提供です。10/10にメールにてご案内します。
- 受講に必要なもの
- ●受講にあたって、Eメールアドレス、Microsoft WordもしくはWordファイルに対応したソフトを所有し、基本操作ができることが条件となります。
●授業はオンライン会議システム「Zoom」を使用します。「マイク・カメラ機能のあるPC/スマホ/タブレット」が必要です。デバイスの推奨環境等はこちらの【システム要件】でご確認ください。
- オンライン説明会
- 講座の内容や仕事のサポートについて紹介いたします。
※ご予約はこちら
同講座の他クラスはこちら
まずは当校の特徴を知りたい方に
学校ガイド(電子ブック)をお送りします
学校ガイドを受け取る